1.淡路島と済洲島の類似
2.済州島「耽羅」と倭国との交流
3.「オノゴロ島」は、??
4.淡路は、国生みの重要な地点
5.イザナミは渦潮に消える
1.淡路島と済洲島の類似
淡路は、今では「淡路島」で、「あわじ」と読む。しかし、淡路は「たんろ」とも読める。例えば、「西淡町」の場合は「せいだん」と読むし、大阪の方の「淡輪」では「たんのわ」と読む。 阿波はどうか? 淡路島の「あわ」になるか? 朝鮮半島の済州島は、古代、「耽羅」と書いて「タムラ」と読まれている。 ただ、「耽羅」は「トムラ」とも読める。 いすれにしても「タンロ」「トムラ」と「タムラ」は語感的にも非常に似ている。この類似点は何か、古代に遡る。トムタレの「トム」は「頭無」であり、「タレ」は古代朝鮮語で「山」を意味する。 また「コムナリ」は「熊津」であり、私達も良く知っている「西成」は「ニシナリ」、すなわち、上町台地の西にあった「津」の意味である。
済州島
2.済州島「耽羅」と倭国との交流
地図を見れば、済州島から対馬海流にのれば筑紫方面へ流れるか?また半島の西海岸を伝わってきた者にとって、済州島へ渡るのは始めての外洋だろう。
済州島は、日本書紀で最初に出て来るのは4世紀後半、太古から登場する。日本書紀に寄れば、済州島は、神功時代は「トムタレ」と呼ばれた。 時代は4世紀後半、半島の「加羅とコムナリ百済」連合軍は、先住民「加耶」から「トムタレ」を奪い、「コムナリ百済」に併合する。
斎明 7年5月(661年)耽羅から始めての入朝。
遣唐使の船、中国越州からの帰路、西南の風に乗り、漂流 耽羅に到着するとある。 彼らは耽羅国の人と一緒に倭国へ行く。 これが耽羅国の具体的な始まりである。 「耽羅」が日本書紀に貢献する国の形で登場するのは、もう少し後の、7世紀後半、天智、天武の頃である。「耽羅」なぜ、その頃、倭国と頻繁に行き来するようになったのだろうか?
---------------資料--(1)-------
天智 4年8月(665年) 来朝 (この頃、筑紫防衛のため 水城を築く)
5年春 (666年)王子「姑如」貢献
6年7月 (667年)貢献
天武 元年6月 (672年)王子 「久麻芸、都羅、宇麻等」朝献
天智の喪は許さず、天武の賀謄極のみ受け入れる。
以降、日本の官位をもらう。
4年9月(675年) 耽羅王 「姑如」 難波へ
5年7月 (676年) 耽羅王 帰る
6年8月 (678年) 王子都羅 朝献
持統 2年8月 (688年) 方物献上 (天武死んでまもない頃、慟哭のとき
3.「オノゴロ島」は、?
日本書紀、古事記の神代記では、数々の話が挿入されている。 その中でも、日本建国の中心となったのは以下の集団である。
-----------------資料--(2)---日本書紀、古事記から--------------
[ 第一 ] オノゴロ嶋 、大日本豊秋津洲、淡路洲、伊予二名、筑紫、隠岐、佐渡、越、
吉備子洲
[第二] オノゴロ嶋
[第三] オノゴロ嶋
[第四] オノゴロ嶋
[第五]
[第六] まず淡路洲、淡洲を胞として大日本豊秋津洲を生む、伊予、筑紫、隠岐、佐渡、越、大洲、小洲
[第七] まず淡路洲を生む。大日本豊秋津洲、伊予二名、隠岐、佐渡、筑紫、壱岐、対馬
[第八] オノゴロ嶋を胞として淡路洲を生む。 大日本豊秋津洲、伊予二名、筑紫、吉備子洲、
隠岐、佐渡、越
[第九] 淡路洲を胞として大日本豊秋津洲を生む、淡、伊予二名、隠岐、佐渡、筑紫、吉備子洲、大洲
[第十] 淡路、蛭児
古事記 ヒルコ、淡島
淡道の穂の狭別島、伊予二名島、隠岐三つ子島、筑紫島(筑紫、豊、肥、熊曾)、
伊岐、津島、佐渡、大倭豊秋津島
吉備児島、小豆島、大島、女島、知かの島(五島列島)両児島(男女群島)
----------------------------------------
4.淡路が重要な地点
そしたら、淡路島はどうか? よくみると、第六書以降、、七、八、九書とも、「淡路」が重要な地点となっている。 この集団は「物部」系 ---時代はことなっても「鮮卑」系の移住ルート
[第六] まず淡路洲、淡洲を
[第七] まず淡路洲を生む。
「第八] オノゴロ嶋を胞として淡路洲を生む。
[第九] 淡路洲を胞として大日本豊秋津洲を生む
初期の狗邪系 は「オノゴロ」を経由、後代の加羅は淡路が上陸地!!
加羅系鮮卑 にとって 「淡路島」は国生みの原点である。つまり、古代、倭へやって来た狗邪系や加羅系の脳裏には、淡路島が重要な地点として焼き付けられている。 この島に済州島の古代名「耽羅」と似た発音、同じ「淡路」と名づけた。
何故、重要な地点か?それは、淡路島の地形的環境、即ち、北端は明石海峡、南端は鳴門海峡
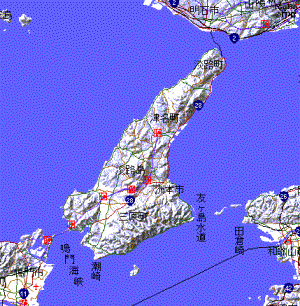
であることを考えれば良い。
イザナキ伊奘諾の死
古代、この海峡の渦潮を乗り切っていく事は至難の技であったろうと思う。それを考えれば、淡路島に「イザナキ神宮」があることは示唆に富む。
日本書紀本文では「イザナキ伊奘諾尊は幽宮を淡路の洲に造り、静かに、長く隠れましき。」とあり、これが伊奘諾尊イザナキ神宮の由来であるが、日本書紀の舞台は淡路である。
古事記--伊邪那岐命、伊邪那美命
日本書紀--伊奘諾尊、伊奘再尊
古事記では、イザナキ伊邪那岐命は淡海の多賀大社に座すと.あり、また伊邪那美命イザナミ神は出雲と伯伎との堺の比婆の山にとある。これを見ると、古事記は明らかに山陰を舞台としている。
ここで、注意点は
伊奘諾神宮-----狗邪、加羅系 --物部 四国から淡路、紀、大和
多賀大社 ---駕洛任那系 --筑紫、出雲、敦賀から近江へ
という勢力分布を考えれば良い。淡路のイザナキは加羅系である。
イザナミは渦潮に消える
国生みの話しの次は、イザナキ伊奘諾、イザナミの性の営みから子供達が誕生する話に移る。 その中で、最後に、イザナミは火の神を生む時、陰が焼けて死んでしまう。イザナミが火神に焼かれて死んでしまう話は、第一書を除いて、全てに記載されている。
ここで問題は
(1) 第1書 高麗系には記載なし。
(2) このイザナミの死から「禊」の話が出て、住吉三神、航海の神が誕生。 、
(3) 日神、ツキヨミ命、スサノオ命の誕生。
第一 高麗 ------ 夫餘、 南方呉、倭
第六 加羅 -------鮮卑、北方漢 夫餘
この話は第六書(加羅系)に詳しいが、火の神でイザナミが亡くなる話は、第一書以外、全てにある。
加羅系は本来、鮮卑主体で、騎馬民族の要素が強い。
かれらにとって、海は神であったろう。 高麗系は南方呉と倭がはいるので、海の航海は得意である。
イザナキ伊奘諾神宮 ( 一宮町 多賀 )
イザナキ伊奘諾神宮の「神宮」の意味は大きい。 住吉大社は「大社」で、イザナキ伊奘諾神宮は「神宮」である。
「神宮」というと、半島から渡来した「加羅」、すなわち物部と関係が深いことを示唆している。
やはり、淡路島は「加羅」系、即ち、鮮卑系騎馬民族に関係あり、航海術にたけた南方系「任那加耶」にとって淡路島は関係が少ないようである。 ここでイザナミの死と淡路島の両端の潮流を考えて見る。
第一書の高麗系は、はるか朝鮮半島の付け根から海路で渡ってきた集団であり、海に強い。 第六書は、加羅からの移住で、本来、騎馬民族で海には弱い。 彼らは、淡路島の潮流を乗り切れなくて、難儀した事であろう。
物部の関連の神社をざっと当ると、その開拓ルートが判る。
築、肥、豊
伊予、讃岐、阿波、淡路、但馬、播磨、摂津、山背
近江、紀伊、伊勢、尾張、岐阜、美濃、信濃、越後
武蔵、下総、常陸、陸奥
彼らは、筑紫から 伊予に周り、四国北岸沿い、そして淡路に繋がる。 どうも、瀬戸内の山陽側は痕跡も少ない。 これで考えると、鳴門の渦潮は物部系に関係ありそうな雰囲気。物部系の「第六書」の物語は、禊の場所、住吉大神、安曇連の神等、航海と海の神に詳しい。 イザナミの死後、禊は筑紫の海である。
またこの集団が半島から渡海する際、守護神として天照大神が誕生する。
イザナミの死は、半島加耶系が、明石海峡や鳴門海峡を乗り切る際に生まれた伝承だと思う。
表紙に戻る