仁徳天皇陵
加耶古代史観から天皇陵の謎に迫る
結論 1.古墳は交通の要所にある。
2.前方後円墳 の向きは 地形に合わせる
3.御陵は新規開拓の地
仁徳天皇陵は5世紀半ばの築城
伝履中、反正陵古墳は、履仲、反正ではない。
反正陵古墳
仁徳天皇陵
加耶古代史観から天皇陵の謎に迫る
結論 1.古墳は交通の要所にある。
2.前方後円墳 の向きは 地形に合わせる
3.御陵は新規開拓の地
仁徳天皇陵は5世紀半ばの築城
伝履中、反正陵古墳は、履仲、反正ではない。
反正陵古墳

実家の堺市砂道から東、浅香山の方に歩くと、昔十三間道路といった幹線道路を渡り、道はやや上り坂となる。さらに南海荒野本線の線路を越えると、上りきった感じになる。小さい頃はまわりには溜池が多かったものだが、今 訪れると住宅ばかりである。 古代の道はどこか定かではないが、それは、住吉大社から南へ高台を南下、遠里小野、浅香山、今池を通り、三国ヶ丘の方違神社まで続く。そこは「反正稜古墳」の前面にあたる。反正稜古墳のすぐ周りまで住宅街が迫っている。(伝反正天皇陵へは、南海高野線 堺東駅下車 cf。古墳探索)
反正稜古墳 円部 方違神社から垣間見る
(考古学的には、仁徳稜古墳より古くて、5世紀前半とか)
仁徳十四年「今年、大道を京の中に作る。南の門より直に指して、丹比邑に至る」
日本書紀によるこの古代の道はどれだろうか?
問題は 「南の門」である。 地図上で、直に丹比を指す道は残存しているか?
果たしてそれはあった。丁度、この方違神社を起点として、東に延びる道である。ほぼ、直線的に、JR堺市駅の南を通り、東へ延び、松原警察、雄略陵古墳、藤井寺小学校あたりに続く。それからは、現在では定かではないが、更に東へ伸ばすと大和川と石河の合流地点あたりに到る。
堺市の十字マークのところから真東に伸びる。--丹比道もう一つ、マークのした仁徳の円部から、やや曲がりながらも東に行くのが「竹内街道」現在では、この道筋にほぼ平行して、堺羽曳野線が走る。この道は、反正稜古墳の前面から起点して、東進して、羽曳野の允尭陵古墳の前面あたりに続く。
この直に指す道が、この道とすると、仁徳の「南の門」は、方違神社あたり、反正稜古墳の前面にあったことになる。さらに「京の中に作る」から見ると、三国ヶ丘から丹比あたりまで、この道路の沿線一帯が京となる。
反正稜古墳の向こうは我が母校「三国ヶ丘高校」がある。それを横手に見て南下すると、後の竹内街道と、西高野道の分岐に出る。ここまで来ると、中央環状線の騒音も近く、この右手向こうには「仁徳稜古墳」が聳える。
左、武内街道 右 西高野道 分岐点
中央環状線の横断歩道の上から 南、仁徳稜古墳を見る。 ここは仁徳稜古墳の前面にあたり、古墳を拝むのに、丁度よい場所である。 古代は、この道路もなく、ここから仁徳天皇陵を拝んだものだろう。
竹内街道は、この仁徳天皇陵の円部から誉田御廟山古墳(伝応神陵、実は雄略天皇陵)の円部にある誉田八幡宮へと続く。西高野街道も高野山まで続く道で、現在でも健在である。武内街道は、現在では中央環状線として道路は東進、仁徳稜古墳の前面を起点として、羽曳野の応神陵古墳に前途を塞がれるように応神陵古墳の前面まで続く。先ほどの反正稜古墳と允尭陵古墳、さらに仁徳稜古墳と応神陵古墳が、おのおの古くは街道で結ばれていたことになる。
古墳の位置は全く人里離れたところでなく、街道の分岐点とか交通の要所にあることがわかる。
仁徳稜古墳
道路を横断歩道で渡ると、直ぐ傍が濠で、満々と水をたたえる。 西側に回りこむ。 ホテル街の風景は御陵には合わないが、すぐ公園となる。 静かな散策道が続く。 見えるのは最も外側の濠で、三重の濠になっている。
この最外側の濠は明治時代に掘られたらしい。
かっては御陵の上まで上がり、花見を楽しんだようである。 こんなにがんじがらめになったのは明治以降。
(考古学的には5世紀半ば、築造) 記紀の年数で行くと、4世紀末になるが。
仁徳稜古墳
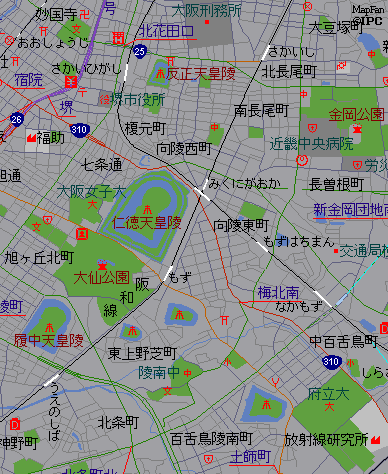
前方後円墳の位置、向き等、立地条件について考える。
位置 円部は交通の要所
円部は、地形的に高所
応神陵古墳にしても、八幡宮があるのは「円」の方である。だから、通説では前方後円墳と呼ばれるが、本当は「前円後方墳」と呼ぶべきであろう。宮内庁による「拝所」は「後方」にあるが、古代より、「円部」の方が「拝所」である。
反正稜古墳 方違神社 ---丹比道の起点-
印恭陵古墳 土師ノ里
応神陵古墳 誉田八幡宮----
仁徳稜古墳 竹内街道と西高野街道の分岐
これら全ては円部の方に位置する。
さらに、向きについて
百舌鳥野古墳群(反正、仁徳、履仲)は南北に。 百舌鳥のニサンザイ、御廟山、イタスケは、東西方向になる。 これは長辺に沿って水が流れるように造作。 本来は、御陵の濠は灌漑用水である。 いわゆる円部から入って、灌漑用水は「方部」から出て行く。 だから、円部を高地にする。 例えば、百舌鳥三陵はと南北に並ぶ。 北の三国ヶ丘あたりがこの辺の高所で、そこから南へ石津方面へは降る。 履中あたりまで来ると、殆ど平地に近くなる。
ニサンザイ、御廟山、イタスケは、百舌鳥川に沿って東西で、円部は東である。
この街道沿線は、今でも溜池が多いところである。さらに羽曳野周辺は、百舌鳥野よりも御陵が豊富かつ、分布面積も広い。地理的に見ても昔の大和川を遡った台地周辺で、石河との合流地点は、重要な拠点だったろう。
百舌鳥野にいた集団の最初の上陸地点が住吉大社、即ち、難波津から始まったとすると、羽曳野に構えた集団ははどこからきたか?古代は、今の大和川は、もっと北へ流れ、上町台地の東は「河内潟」とよばれる湿地帯であった。氾濫も繰り返すところには移住しにくい。
羽曳野を考えるに、鍵となる記事は、日本書紀の以下の三点。
(1)「堀江」の大工事、茨田堤
(2)丹比道
(3)「石河」の大溝
垂仁の時代は、高台の丘陵地帯での稲作で、工事の主体は灌漑用溜池をつくることであった。仁徳の時代になると、河の流れを変えて低湿地を稲作可能な土地にかえることになる。さらに河の堤防を築いて、氾濫を防止する工事も行なう。
仁徳十一年 冬十月、宮の北の郊原を掘りて、南の水を引いて西の海に入る。因りて其の水を号して堀江と云う。又将に北の河の澇を防かむとして、茨田堤を築く
仁徳十二年 冬十月、大溝を山背の栗隈県に堀って田に潤く。是を以って、其の百姓、毎年 豊。
この年、朝貢してきた、新羅人をこの役に使っている。当時、4世紀前半は倭国と新羅は花嫁をやりとりする仲だった。-------
垂仁の時代は、川内の丘陵地帯であったが、仁徳になって難波にも進出した。 河内潟を開拓して、それを稲作可能な地帯にしたのが「仁徳」の時代である。仁徳の時代、和泉から河内のどの辺まで進出していただろうか?
仁徳十四年 今年、大道を京の中に作る。南の門より直に指して、丹比邑に至る。また、大溝を感玖に掘る。すなわち石河の水を引いて、上鈴鹿、下鈴鹿、上豊浦、下豊浦、四処の郊原に潤けて、墾りて四万余頃の田を得たり。故、其の処の百姓、寛に饒ひて、凶年之患無し。
石河は、丁度、羽曳野あたりで大和川に合流する川で、允尭陵古墳もその直ぐ傍らである。四所の郊原の所在は不明とあるが、羽曳野あたりであろう。
堀江の大工事で、逆流による氾濫も少なくなり、大和川の下流も住居可能になる。そこへは都から幹線道路を引く。更に石河の大溝工事の完工で、溜池に水を引き、田植えも出来るよう。
以上、和泉からは、丹比道を引いて、石川から運河を引いて羽曳野を潤す。 つまり、御陵は人里離れたところではなく、彼ら、新規開拓した地に造られた。
履中陵古墳
どれが誰の御陵なのか、?を」考察。
仁徳稜古墳から南へ歩く。 広大な大仙公園を通ると、前方には「履中陵古墳」が間じかに見える。抜けると、目の前に履中陵古墳が現れる。ここまで来ると、例の三国ヶ丘から下がってきた感じで、低地の感じがする。道路の向こうは潰れた店なのか、人影もなく、その駐車場の金網越しに拝む。
履中陵古墳 円部から金網越しに望む。
履中陵古墳の東方には、イタスケ古墳、御廟山古墳、ニサンザイ古墳と反正、仁徳、履中古墳群とは、九十度近く方向を換えて、東を向いて並ぶ。大きさから見るとかなりの勢力を連想されるが、記紀の記載は、仁徳、履中、反正だけである。
履中陵古墳の周囲は散策道があって閑静な住宅街である。 円部から西側を巡り、周囲をぐるいと周り、JR「上野芝」の駅に出る。
履中即位前期に、住吉仲皇子(仁徳の第二皇子)が叛いて殺される記事がある。問題を解く鍵を与える物語である。 微妙に違う。
まず当事者 日本書紀: 住吉仲皇子(仁徳の第二皇子
古事記: 墨江中王で、他の皇子のように「ミコト」と呼ばれていない。反乱のきっかけ
日本書紀 :
住吉仲皇子は太子の名前を語って「黒媛」を犯す。それがばれそうになって、太子を殺そうとして、兵を上げたとある。
古事記:
古事記では、墨江中王の反逆とされ、墨江中王が天皇を取らんと欲して、大殿に火をつけたとある。
履中側の勢力分布
日本書紀」:太子(履中)、 平群つくの宿禰。 物部大前宿禰、漢直の祖阿知使主
古事記: 漢直の祖、阿知直のみで、平群、物部は見えない。
住吉仲皇子側の援軍日本書紀:安曇連浜子や倭直吾子籠で、名前から見て海洋系の色彩が濃いか。
古事記:
日本書紀
端歯別皇子(後の反正)、太子から 難波の仲皇子暗殺を強いられる。困った皇子は隼人の刺領巾に暗殺の実行を依頼。刺領巾は一人、矛を取って、太子の厠に入るを伺って刺し殺す。
一方、実行犯は「隼人」で、履中、平群つくの宿禰によって処分される。よって履中は。盤余稚桜宮で即位。古事記
、墨江中王の反逆とされ、難波宮から履中を救い出すのは漢直の祖、阿知直である。暗殺実行後、実行犯の隼人が酒を飲むときに、隼人の首を切ってしまう。そこを「近飛鳥」(河内の飛鳥)と言う。また明日、大和の石上神宮に参るということで、そこを「遠飛鳥」と言う。阿知使主が殊勲者として戦後表彰を受ける。