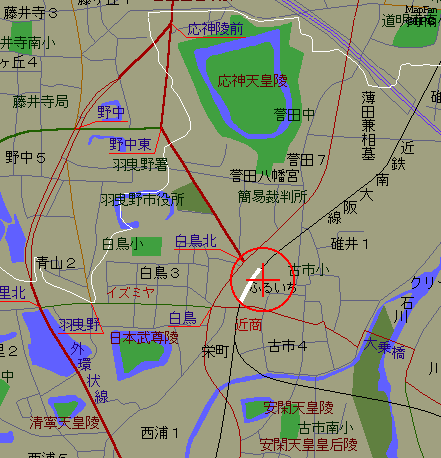誉田御廟山古墳(応神天皇陵) 5世紀半ばに築かれたとされる。
墳丘の長さでは仁徳稜古墳に次いで2番目の大きさ。 体積では日本一である。

八幡宮に入り、社殿を真正面に見て、右に入る。 ここから誉田八幡宮から望む。 前方の太鼓橋が「放生橋」、かっては古墳の上まで、神輿が上がっていたらしい。 橋の手前までしか行けない。
誉田八幡宮の片隅、御陵よりに当宗神社 あり、祭神は、当初、朝鮮の楽浪郡から渡来した当宗忌寸の祖神、「山陽公」を祀っていたようだ。 また朝鮮国王から奉納された石灯篭も在る。
放生橋を見て、御陵の方へ向かうが、先は幼稚園で道が判らず、神社を出て迂回、御陵の山をみて進む。
 航空写真〔看板から撮影)
航空写真〔看板から撮影)赤い→のところが、誉田八幡宮
八幡宮を一旦出て、迂回して御陵の方へ向かう。 小さな小川が流れている。 この小川から見れば、やはり「円部」の方が高い。 この川は、津堂城山古墳と伝雄略天皇陵の間を流れている。太古、河内潟から登ってくる道になるかも。 看板の航空写真を見ると、「前方」部のほうは満々と濠に水があるが、「後円」部は大分、干上がっているようである
また西側は東側と様相が違い、田園風景である。 ただ向こうにはトラックが行き交う道路が走る。
畑まで空間があるが、堀端まで行けない。 イチジク畑である
 。
。 これらの畑も、太古は濠であったようだ。 前円部まで回るが、なかなか濠は見えない。
ここでも交通の要所がある。 応神陵の南部、即ち円部のところである。 野中東の交差点を見
南北には170号線に大型トラックが走る。 西からは、堺、羽曳野線がまっすぐ走る。 古代の武内街道にほぼそろう。 この東西に伸びる道路も興味深い。
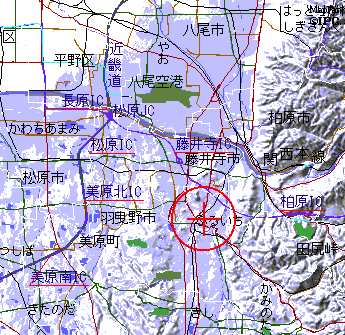
誉田山古墳の位置
 右 大峰山
右 大峰山