印恭天皇陵
仁徳 313-399
履中 400--405
反正 406--411
印尭 412--453
応神 390--433
雄略 457--479
太古の交通の要所
近鉄南大阪線土師ノ里駅を降りると、直ぐの交差点が土師ノ里の交差点。 丁度、高台の上にあるのが判るし、南北に伸びる国道(旧170号線)、東西に伸びる道路交点で、交通の要所というのが実感できる。
交差点の北東がわ向こうには市野山古墳(允恭天皇陵) 、南西方向には仲ツ山古墳(仲津姫皇后陵」)が、円部を突き合わすように配置されている。 両者の円部の交差が」土師の里である。
これから判るようにこれらの古墳は「円部」の方が、古来より重要な位置をしめる。
大概、円部の方が高い位置にある。 丁度、土師ノ里交差r点が最高。。
即ち、灌漑用水の立場で言えば、用水の出口は「方」の方である。
現在では、「拝所」なるものは「前方」にあるが、古来からの拝所は逆である。
今では建物が建てこんで、直ぐには見えないが、太古はすぐそこに眺められたであろう。
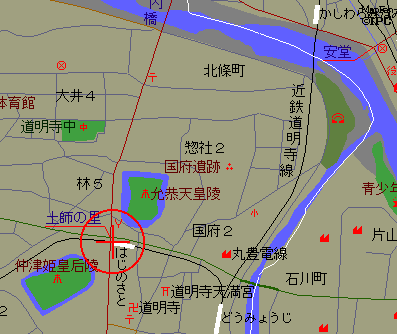
両者は向かい合うように、前方後円墳の円部をあわせるかのように並んでいる。 そして、この交点を通る、
最も、ここは道路用にしたもので、太古の丹比道は、この道路の直ぐ北側、堺から並行して走っている道路が、太古の丹比道に近い。東西の道は仁徳記でも出てくる丹比道である。 この道は反正稜古墳の円部あたり,(堺市、 方違神社)から東へほぼ直線的に伸び、丹比に到っている。
この太古の丹比道は、現在の藤井寺市外で多少とぎれるが、その東端は大和川の石川との分岐点にあたる。
また、土師ノ里交差点を南北に走る道路は、北は生駒山西麓につながり、南は石川に沿って南下して、古市、富田林、河内長野へと続き、以降、高野街道で高野山方面へと続く。 まさに交通の要所である。
近い飛鳥
石川周辺は太古から交通の要所である。 和泉から東に丹比道。 日本書紀仁徳の項でも石河の水を引く話があり、「仁徳」和泉からもここまで進出していた事がわかる。
さらに、ここは大和に入る入り口の起点である。
当時は 大坂 ---二上山の北 「穴虫超」
当麻 ニ上山の南 「竹ノ内超」
竜田山 大和川北岸 「亀の瀬超」
とかが河内の起点が石川と大和川が合流するところ。 r履中は、当初、大阪から越えようとするが、途中合う少女から、この道は先に兵がいるので、当麻道を取るように言われる。 履中は、結局、北の竜田から入る。
さらに、北側 生駒の方から降る道とも合う。 神武東征によると、最初、竜田から入ろうとするが、この道は険しく行くことは出来ず。 生駒山の「草香山」あたりから入ろうとする。しかし、「トミ」の「ナガスネヒコ」に遮られて、後退する。
すなわち、和泉や北河内からの道がここで合い、大和に入る。 仁徳天皇でも触れたが、履仲即位前期の「履中、反正」と「住吉仲皇子」との戦いは、ここ石川の争奪戦争で合った。 この結果、仁徳系は大和へは入れず、大和への進入は、「加羅、新羅、コムナリ加耶」系が握る。 「近い飛鳥」の誕生である。
遠い飛鳥は
結果、大和へ入るのはどの勢力か? 新羅勢力である。 允恭天皇。 この大和進出は、「神武東征」のモデルとなる。 允恭の新羅勢力の大和進出が「遠い飛鳥」である。
先ほどの加羅加耶は「物部」、で、物部は大和先住加耶の討伐に際して、先住加耶「トミ」を裏切り、外来の新羅勢力に荷担。 としても、新羅勢に屈服して、自らは大和に入れず、以降、河内に地盤をl築く。
市野山古墳(允恭天皇陵)仲ツ山古墳(仲津姫皇后陵」)
 市野山古墳(允恭天皇陵)
市野山古墳(允恭天皇陵)
市野山古墳(允恭天皇陵)の周囲は人家が多い。 「前円」部の方はすぐ見つかったが、拝所の「後方」はどこかと探したが、なかなか見つからない。 そこらと思うが、人家が邪魔して行けない。 ようやく探すが、犬にほえられて迷惑。 まこと拝所の直ぐ傍まで人家がある。 また、この陵の濠は何故か空である。
またこの陵に直ぐ近くの仲ツ山古墳(仲津姫皇后陵」)も空である。 土師の里へ戻り、南下すると、右手に小高く見える。 周囲は垣根ごしなので、水がないとしても進入は出来ず。 最近、水を抜いたのか、どうか? 濠には雑草ばかりで、木々は生い茂っていない。
 仲ツ山古墳(仲津姫皇后陵」 円部
仲ツ山古墳(仲津姫皇后陵」 円部
、御陵は水満々のほうが風情がある。 もともと、灌漑用水の為であるが、もうこのあたりは用なしであろう。 としても、濠に水がないのは、なんとしても惨めである。 この陵の場合も人家が濠まで迫っている。 空窟な御陵である。
応神 加耶古代史観
応神は記紀では、応神−−仁徳と続く。 もちろん、応神−−仁徳という具体的に人物が確かにいたことなど不明な事で、詮索の余地が無い。 問題はこれらのl古墳が時代を示唆するものとして意味があるだろうし、それを探りたいことだ。
私の加耶古代史観で行くと、その勢力分布
仁徳--応神は平行する時代で、応神に続くは、「雄略」である。同時代的にみて、関係する集団を書くと、以下のようになる。 4世紀後半から5世紀前半には倭国内には以下の勢力があった。
履中、反正、印尭とも仁徳の子とされるが、実は以下のように。
仁徳-------倭加耶
応神、雄略 ---任那加耶(コムナリ)
履中、反正 ---加羅加耶
印尭 ------新羅
仁徳加耶 任那成立(以前、倭へ摂津移住、 (仁徳天皇)
加羅加耶 半島では 任那成立以後、半島で加羅加耶の勢力が伸張して、新羅を征討したり、コムナリ百済と連合
倭国では、
当初は北河内へ進出、その後、南下、石川流域に迫る。 物部系
先住加耶の仁徳加耶を討伐、石川流域を獲得、(履中、反正天皇) 近飛鳥
さらに、新羅系と通じて、新羅の軍事力に成り下がる。
最後は(、顕宗、仁賢天皇)が平群を討伐、倭先住加耶を殲滅して、天下に近づく。
新羅 新羅は加羅加耶についで、倭国へ進出。 加羅系と連合 (印尭天皇)、大和西北部へ進出。遠飛鳥
応神 任那成立以後、半島で加羅加耶の勢力が伸張して、新羅を征討したり、コムナリ百済と連合、倭国は伸 張する。 その連合は、コムナリ百済にいた任那加耶の一部「応神」が、倭に移住する機会ともなる。
倭国での応神は、当初、加羅加耶と共存するものの、応神に続く「雄略」では、先住加耶「仁徳」、外来加 羅加耶の両者を闘争して、倭国での覇権を狙う。
( 時代は5世紀後半以降)
こう考えると、
御陵の被葬者は?
(1)
履中、反正稜古墳が百舌鳥野にあるのあり得ない。 石川流域が合理的か?
加羅 の進入ルートも北河内から南下。
(2)
新羅の印尭陵は 土師ノ里にあるが、新羅が大和西北部に入れば、向こうに陵が合って良い。
(3)応神は、加羅加耶と連合して入るとなると、北河内から南下
仁徳稜と応神陵は竹内街道で繋がる。 同じルーツ
(4)
仁徳加耶は摂津から東進 、加羅や応神が来る前に、丹比道で石川流域に通じる。
(反正稜と印尭陵は、丹比道で繋がる。)
(5)
亡くなった年代を推測すると 大体以下。
仁徳 313-399
履中 400--405
反正 406--411
印尭 412--453
応神 390--433
雄略 457--479
だから、応神は、ずうと後、仁徳の後である。
仁徳の男子は?
履中、住吉仲皇子、反正、印尭-----葛城系
大草香皇子 ------------日向系
で、履中、反正の二人だけが仁徳稜の傍にあるとされ、印尭はずうとi石川流域にある。他の二人の皇子は、反乱者として消される。 これら「謀叛」がくせものである。
、
住吉仲皇子 反乱とかで、履中、反正(加羅加耶) 隼人に暗殺を依頼。
大草香皇子 根臣の讒言により、安康天皇(新羅系)により殺害される。
等、先住仁徳加耶は 外来加羅、新羅系により殺され、仁徳加耶は途切れてしまうことになる。 だから、これは単なる謀叛ではない。
履中、反正の御陵?
允尭
允尭陵は 大和西北の伝「垂仁天皇陵」が正しいか??
もともと 垂仁天皇は年代的にも3世紀なので、前方後円墳の古墳時代ではない。日本書紀の年では、もっと古代になるので、ますます怪しくなる。 この地域は、トミ いわゆる神武が戦ったトミノナガスネヒコの地盤にも近いし、一山超えれば、例の北河内、物部にも近い。 加羅加耶は当時は、大和川分岐まで進出、新羅勢は加羅勢力の寝返りを待って、トミナガスネヒコを討って、大和へ入る。
さらに、この地は、新羅勢力の場となる。 即ち、東の春日に対して、西ノ京と呼ばれる。 薬師寺とかは天武時代の発案で、新羅系たっぷりである。 これら考えると、大和西北部の丘陵は、新羅が加羅(物部)の協力の元、先住加耶「トミ」を打倒して、新羅勢力がこの地に進出したと考えられる(神武の物語)。
履中、反正
土師ノ里の二陵
北河内からの南下ルート、履中、反正の二人の結束、とか考えると、土師ノ里にある、二つ、頭をよせているのが彼らの御陵とする。 仁徳の時代、摂津から大和川の分岐までの東西の道、それを横切るように南北に走る道、その交点にあるこの二つの御陵の意味は大きい。 この交通の要所を加羅加耶が獲得、後、新羅の大和入りを助ける。
即ち、仁徳加耶の東進、大和への進出を阻み、北から降りてきた加羅加耶が、大和川の合流点を取った。 その戦略地点に二つ、並んでいるのは履中、反正を置いて他に無い。 允尭陵を大和のすれば、当然これが余ってくる。
允尭の男子は?
木梨軽皇子----穴穂天皇即位前期 太子暴虐 (物部大前宿禰の家に逃れて、伊予に流刑
境黒彦皇子----眉輪王と共に、円大臣宅へ逃げて、諸共 焼き殺される。
穴穂天皇-----眉輪王(大草香皇子(仁徳の皇子)の皇子)のために暗殺
八釣白彦皇子 ---雄略即位前期 雄略に斬られる
大泊瀬稚武天皇(雄略)
結局、雄略だけが生き残るが、これまた雄略は新羅系でなく、コムナリ加耶系である。 結局、これは、応神雄略のコムナリ加耶が、当時新羅勢力を征討して天下を獲ることを示唆している。
決して兄弟争いのようなものではない。当時は加羅加耶系もいるが、履中の長子、市辺推磐皇子も、雄略に射殺される。 市辺推磐皇子の子供達は難を逃れて疎開する。
雄略は、新羅系、加羅系を征討して倭国を統一した。だが、日本書紀は、悪しき天皇として描写している。 物部系の意向が強く働いている。 なお、安康陵は、記紀によると、先に私が指摘した垂仁陵古墳の近くにあるとされる。
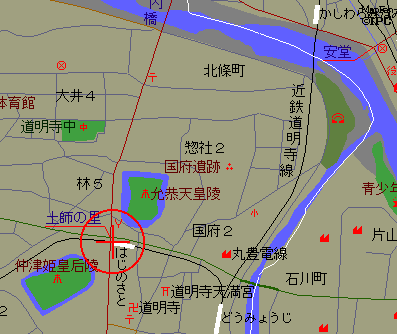
 市野山古墳(允恭天皇陵)
市野山古墳(允恭天皇陵) 仲ツ山古墳(仲津姫皇后陵」 円部
仲ツ山古墳(仲津姫皇后陵」 円部