
 cf.天平彫刻 毛利 久 小学館 ブックオブブックス 日本の美術(5)
cf.天平彫刻 毛利 久 小学館 ブックオブブックス 日本の美術(5)

 cf.天平彫刻 毛利 久 小学館 ブックオブブックス 日本の美術(5)
cf.天平彫刻 毛利 久 小学館 ブックオブブックス 日本の美術(5)
聖林寺観音と同じ作りと言われるが、観音寺十一面観音像はは若い乙女似て写実的で、腰もくびれて臍も丸出しである。
女性の胸を連想するほどのものは、薬師寺金堂の月光菩薩と似て、天平前期の面影を残す。
聖林寺 の観音は、天衣で臍を隠し、臍丸出しは
渡岸寺観音
と似る。 首飾り、胸飾りなどの装飾はない。
1997/3/2
1.観音寺 付近
(交通)近鉄奈良線 西大寺駅で、京都線に乗り換え。「みやまき」下車
もしくは、JR学研都市線を利用すると、大阪市内京橋から乗り換え無しで行ける。「かみたなべ」下車
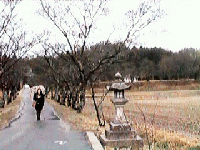 田圃の中、桜並木を歩く。この並木道の突き当たりが観音寺。
田圃の中、桜並木を歩く。この並木道の突き当たりが観音寺。
十一面観世音菩薩は、古記録によると天平16年(744年)に安置されたそうな。 当時は息長山普賢教法寺と称して、五重塔も建立され盛んな大寺であったが、1437年の冬の火事で ほとんど失われてしまったとか。「息長」(おきなが)というのは、古代、現在の滋賀県坂田郡から長浜市あたりで大きな勢力を持っていた「息長氏族」と同じなのか。昔、坂田銀近江町に「息長村」があったそうだが、息長は新羅語という話もあり、興味深い。
参考図書
1.十一面観音の旅 丸山尚一 新潮社
「天武天皇の勅願、義淵僧正の開基を伝える古寺であり、天平期に、良弁僧正の弟子で東大寺二月堂の創建者である実忠和尚が復興して、普賢寺としたといわれる。」
現在まで天平の名残をとどめているのは、ただひとつ「十一面観世音菩薩」 だけ。大火の中、村の人たちは必死で観音像を火事から守ったのであろう。 湖北に残る渡岸寺 の観音と同じく、庶民に守られて後世に伝わっている。両寺とも、他の仏像群は焼けてしまったのに、何故、十一面観音だけが残っているのだろうか。持ち出すに、手ごろな重さだったのか。もしくは観音信仰の深さなのか。

住職さんに案内されて、薄暗い本堂の中に入り、かすかな燈明の明かりで十一面観世音菩薩を拝む。
聖林寺十一面観音のようなガラス越しでなく、お寺の本堂で直に拝めるのはうれしい。あるべきところに在るという感じである。懐中電灯をあてて、デジカメで撮る。光背と十一面観音頭部の金箔だけが、かすかに写る。もっとも、金箔は殆ど剥げ落ちており、黒漆の地がでているので
写りにくいことは確か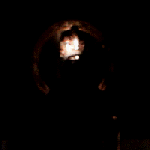
はるか彼方、天平の時代にタイムスリップ。合掌。
------------
天平12年から17年にかけての、遷都に次ぐ遷都が行われた。そのうちのひとつ恭仁宮は木津川の対岸、観音寺の東方
約10km。
Please send your impression to the
following address eizobach@ta2.so-net.ne.jp